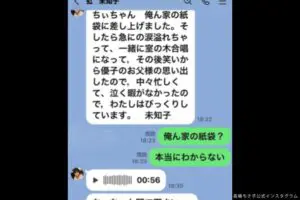日本一厳しい重量制限、驚きの数値に目を疑う… 「通れません」と諦めるネット民続出
とある橋で見かけた、古びた重量制限の標識。その「予想外すぎる数値」に、驚きの声が寄せられていたのだ…。
街を歩けば至るところで目にするのが、道路上の案内標識。風景に溶け込んでいることも多く、普段であればあまり気にならない存在である。
しかし以前ツイッター上では「予想外すぎる数値」の表記された標識に、多数のツッコミが寄せられていたのだ…。
【関連記事】日本一強気な道路標識、その内容に目を疑う… 想定外すぎる「4文字」が話題に
画像をもっと見る
■この制限標識、何かがおかしい…
今回まず注目したいのは、日本各地で生きる人々の生活や昔の記憶、伝承などを記録して著作にまとめている紀行写真家・道民の人さんが投稿した1件のツイート。こちらの投稿には橋を写した写真がいくつか添えられており、赤錆の目立つ「重量制限標識」の様子が確認できる。

果たして重量制限はいかほどか、と目をやると…そこには「0.1t」と、予想していたよりも遥かに小さい、否「小さすぎる」数値が表示されていたのだ。
■「大人2人すら乗れないのか」と驚き

「近畿地方に存在する、おそらく日本で一番軽い数字の重量制限標識。古い橋には5.5tなど車両重量制限を示す丸い標識があるが稀に1t以下のものがあり、中でもこれは最小の重さ」「吊り橋とはいえ100kgとかバイクはむろん人間でも制限引っかかるヤツいるぞ。ここ以外で見たことがない破格の数だ」と綴られたツイートは、写真のインパクトもあってかツイッター上で大きな話題に。
投稿から数日で6,000件以上ものRTを記録し、他のツイッターユーザーからは「自分、0.1t超えてるので渡れません…」「ダイエットしてから渡れ、ということか」「大雪降っただけでアウトになりそう」「大人2人すら駄目なのか」などなど、驚きの声が多数寄せられていた。

ツイート投稿主・道民の人さんに詳しい話を聞くと、こちらの写真は和歌山県那智勝浦町南大居地区にある「筑紫橋」にて撮影したものと判明。
そこで今回は「驚きの重量制限」の背景をめぐり、ツリー投稿にて熱い探究心を見せてくれた道民の人さんの意思を受け継ぐ形で、筑紫橋を管理する「那智勝浦町建設課管理係」に詳しい話を聞いてみることに。その結果、様々な事実が明らかになったのだ…。
■橋の歴史、あまりに謎すぎるが…
今回の取材にあたり、那智勝浦町建設課管理係担当者は「吊り橋部分を『築紫橋第1』、吊り橋でない部分を『築紫橋第2』という名称で、町道南大居10号線内の橋梁として管理しております」「築紫橋第1は、2011年の水害によって落橋し、架け替えられた経緯があります」と説明している。
事情を聞くと、こちらの落橋をきっかけに「重量制限」が設けられたように感じられるエピソードだが…担当者からは「11年に落橋した際の現場写真を見ても同標識が確認できるため、11年以前から設置されていたことは間違いないと思われます」「設置時期については、いつ頃設置されたものか分かる資料が保管されていないため、不明となります」との回答が得られ、謎はさらに深まるばかり。

そこで、主題を標識の「歴史」から「耐久性」にスライドし、取材を続行することに。
「0.1t」表記の真偽について、担当者は「11年に落橋した後、橋を架け替えるに当たって、耐荷重を0.1tとして設計を行なっております。実際には数値上の余裕が設けられておりますので、橋の上に0.1t を超過するものがのった場合、即座に落橋するという数値ではございません」と説明している。
こちらの標識のほか具体的な条件は設定されていないが、橋の幅員が 1.6m以下である点を考慮すると、実際に通行できる車両は自転車、バイク、トラクター等に限られる、というのが担当者の見解であった。
また、対荷重決定の背景については「築紫橋第1を含む南大居10号線は、築紫地区にお住いの方々の生活道であり、現在でも自転車・徒歩で郵便局や商店に向かう際の最短ルートです」「他方、現在は車両の通行できる築紫土光作線(道民の人さんのツリー投稿にもあった「崖を越える車道」)が整備されており、車両での移動に関しては南大居10号線を通行する必要がありません。このような経緯から、耐荷重0.1tでの設計になったものと考えられます」とも分析していたのだ。

前出の説明のように「100kgはあくまで目安」だが、重要なのは地元民らにとって重要な橋であるという点。
担当者は「築紫地区をはじめ、周辺は田園風景の広がるのどかな土地であり、ツーリング等で訪れる方も多いかと存じますが、築紫橋第1は地域の方の生活道であるという点を鑑み、重量制限を守ったうえで、大切にご利用くださいますようお願いします」と、注意を喚起していた。
こうした「珍しい標識」を発見した際は、道民の人さんのように「歴史的背景」や「地元の人々らの生活」に思いを馳せると、新たな発見があるかもしれない。